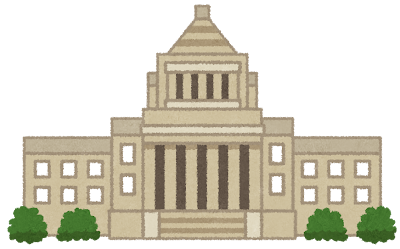今年の所得税、来年の住民税|札幌で税理士・公認会計士に無料相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ!
2025/04/04
目次
はじめに
令和7年(2025年)度税制改正法案は少数与党下の国会での紆余曲折を経て3月31日の年度末ギリギリで、年度予算案とともに成立しました。今回の税制改正の内容については昨年の年度末に以下の記事をアップしていますが、今回は報道されている通り各党との議論の過程で当初の税制改正法案から修正がされており、特に国民の関心が高く今年の参議院選挙でのアピールポイントになりやすい所得税関連の改正がメインになっています。
参考記事:令和7年度与党税制改正大綱
今回は成立し確定した所得税の改正内容のうち、多くの人に影響がある改正事項を取り上げ今後の所得税がどうなるのかご理解いただけることを狙いとしています。なお、改正内容は翌年6月以降の住民税(個人都道府県民税及び個人市町村民税)にも影響するため、来年令和8年度の住民税への影響についても併せて説明します。
なお、改正法案については以下のリンクもご参考ください。
基礎控除の引き上げ
今回の税制改正でほとんどの人に影響するのが基礎控除額の引き上げです。当初の改正案では、合計所得金額(各種所得控除適用前の所得)が2350万円以下の場合に現行48万円から10万円多い58万円に引き上げるとされていました。改正理由は平均所得水準上昇に伴う課税所得の下限引き上げなのですが、国会での議論の中でいわゆる年収の壁に配慮し課税所得下限をさらに上げるべきだとの意見があり、以下の通り修正されました。
- 令和7年(2025年)・令和8年(2026年)における基礎控除額の一覧
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 |
|
336万円超489万円以下 |
68万円 |
|
489万円超655万円以下 |
63万円 |
| 655万円超2350万円以下 | 58万円 |
| 2350万円超2400万円以下 | 48万円 |
|
2400万円超2450万円以下 |
32万円 |
| 2450万円超2500万円以下 | 16万円 |
| 2500万円超 | なし |
- 令和9年(2027年)から当面の間における基礎控除額の一覧
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超2350万円以下 | 58万円 |
| 2350万円超2400万円以下 | 48万円 |
| 2400万円超2450万円以下 | 32万円 |
| 2450万円超2500万円以下 | 16万円 |
| 2500万円超 | なし |
なお、上記の基礎控除引き上げは所得税のみで住民税については現行と変更なく基礎控除額の引き上げはありません。参考までに住民税における基礎控除額の一覧を掲げます。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
| 2400万円以下 | 43万円 |
| 2400万円超2450万円以下 | 29万円 |
| 2450万円超2500万円以下 | 15万円 |
| 2500万円超 | なし |
給与所得控除額の引き上げ
今回の改正では給与所得を計算する際に給与収入から控除する金額も引き上げられ、こちらは基礎控除とは異なり住民税の計算においても控除額が引き上げられます。主な理由は低所得者の賃金引上げ促進で、対象者は年間の給与収入が360万円以下の方です。具体的な変更額は、
- 給与収入が162.5万円以下 55万円→65万円
- 給与収入が162.5万円超180万円以下 給与収入×40%-10万円→65万円
- 給与収入が180万円超190万円以下 給与収入×30%+8万円→65万円
- 給与収入が190万円超 現行通り
です。改正後の給与所得控除の一覧を示すと以下の通りです。ここでいう給与収入には通勤手当や出張日当・実費など所得税非課税とされるものは除外されますのでご注意ください。
| 課税給与収入 | 給与収入からの控除額 |
| 190万円以下 | 65万円 |
| 190万円超360万円以下 | 課税給与収入×30%+8万円 |
| 360万円超660万円以下 | 課税給与収入×20%+44万円 |
| 660万円超850万円以下 | 課税給与収入×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 |
新しい扶養家族控除の新設
今回の改正では学生世代のご家族のいる方について、アルバイト等の就労調整をせずに済むよう扶養者に適用される新たな控除が新設されました。名称は「特定親族特別控除」といい、特定親族とは対象年度の12月31日時点で居住者と生計を一にする19歳から22歳までの親族(配偶者を除く)及び里親として保護している児童(いわゆる里子)で、青色事業専従者として届け出ている者ではない合計所得金額が一定金額以下の者をいいます。控除は特定親族1人単位で適用され該当する家族が2人以上いる場合はそれぞれ適用できます。一方、控除の適用は例えば夫婦共働きなど同一生計内に複数の所得者がいる場合いずれか1人に限られ二重適用はできませんのでご注意ください。
この特定親族特別控除は住民税にも新設されていますが、控除額が所得税と異なります。以下に所得税、住民税それぞれの控除額を掲げます。
- 令和7年(2025年)度以降の所得税における特定親族特別控除額
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
| 85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超90万円未満 | 61万円 |
| 90万円以上95万円未満 | 51万円 |
| 95万円以上100万円未満 | 41万円 |
| 100万円以上105万円未満 | 31万円 |
| 105万円以上110万円未満 | 21万円 |
| 110万円以上115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
- 令和8年(2025年)度以降の住民税における特定親族特別控除額
| 前年の特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
| 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円以上100万円未満 | 41万円 |
| 100万円以上105万円未満 | 31万円 |
| 105万円以上110万円未満 | 21万円 |
| 110万円以上115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
iDecoの拠出限度額引き上げ
今回の改正では老後資金の充実と投資へのシフトを後押しする観点から個人型確定拠出年金(iDeco)の掛金拠出限度額を以下の通り引き上げる旨の確定拠出年金法改正が行われる場合でも、1年間の掛金全額について小規模企業共済掛金等控除として所得控除ができる取り扱いを継続することになりました。
- 第1号保険者(自営業者など国民年金加入者):月額68000円(国民年金基金との合算)→月額75000円(国民年金基金との合算)
- 第2号保険者(会社員など厚生年金加入者):月額20000円(企業型DC加入)または月額23000円(企業型DC非加入)→月額62000円(企業型DCとの合算)
- 第3号保険者(厚生年金加入者の配偶者):月額23000円から変更なし
なお、記事アップ時点では確定拠出年金法改正法案は提出されておらず成立および施行時期は未定です。
(子育て世代向け)生命保険料控除の拡充
今回の改正では令和8年(2026年)分の所得税における2012年以降加入の生命保険料控除について、令和8年(2026年)12月31日時点で23歳未満の扶養親族がいる居住者においては以下の通りとなり通常の控除額よりも拡大されます。
- 年間掛金合計3万円(通常は2万円)以下:掛金全額
- 年間掛金合計3万円超6万円以下(通常は2万円超4万円以下):15000円+掛金×50%(通常:10000円+掛金×50%)
- 年間掛金合計6万円超12万円以下(通常は4万円超8万円以下):30000円+掛金×25%(通常:20000円+掛金×25%)
- 年間掛金合計12万円(通常は8万円超):60000円(通常:40000円)
この拡充は出費の多い子育て世代に配慮するためであると思われますが、住民税においては今回の控除額拡充措置はありません。
おわりに
今回は令和7年税制改正のうち所得税及び住民税の計算に影響する主な改正点について取り上げました。ここで改正に伴う実務的な留意点についてお話します。特定親族特別控除については人的控除に該当するため年末調整段階で反映させることができます。そのため、年末調整書類にも変更が加わる見通しです。年末調整における今回の所得税改正に関する留意点については年末調整の時期が近づきましたら改めてアップ予定です。